五・一五事件は、1932年(昭和7年)に起きた軍部によるクーデターです。内閣総理大臣・犬養毅が暗殺されるという重大な政治事件になりました。
なぜこの事件が起きたのか、どのような背景と経緯があったのかを解説するとともに、その後の二・二六事件や日本社会への影響についても詳しく紹介します。
本記事では、五・一五事件に関する新聞報道や政治的な動きも取り上げ、事件が現代に与える意味を探ります。
五一五事件とは?その背景と概要
まず、五・一五事件とは何なのか、その概要と事件発生の背景をまとめました。
五一五事件はいつ起きたのか?
五・一五事件は、1932年(昭和7年)5月15日に発生しました。若手海軍将校や右翼団体の関係者が、内閣総理大臣であった犬養毅の暗殺を含む一連のクーデターを企てました。
襲撃は首相官邸を中心に、東京市内の複数の場所で同時に行われました。
襲撃の対象には、犬養毅のいた首相官邸だけでなく、政財界や警察関係者も含まれており、暴力的な行動によって軍部が政治に影響力を持とうとする象徴的な出来事となりました。
この事件は、日本における立憲政治の崩壊を象徴する重要な転換点として歴史に刻まれています。襲撃後、軍部が徐々に政治への介入を強め、後の二・二六事件や軍国主義の台頭へとつながるきっかけとなりました。
なお、二・二六事件については以下の記事で詳しく解説しています。
二・二六事件の真相と影響: 日本政治を揺るがした皇道派・青年将校の反乱はなぜ起きたのか
なぜ五一五事件は起きたのか?
五・一五事件が発生した背景には、複雑な社会的・政治的要因が存在します。
まず、大きな要因の一つは世界恐慌(1929年)による深刻な経済不況です。日本は輸出依存型の経済構造を持っていたため、世界的な不況が国内経済に大打撃を与え、失業率の上昇や農村部の疲弊が進みました。
不況から脱しようと浜口雄幸内閣が金輸出解禁を決めましたが、短期的には逆効果となってしまいました。
※浜口雄幸についてはこちらの記事で解説しています。

さらに、昭和初期の日本では、政治に対する不信感が国民の間で高まっていました。特に、政党政治の腐敗や政財界の癒着が批判される中で、軍部は「国を立て直す」という名目で政治に介入しようとする動きを強めていました。
これに加えて、満州事変(1931年)後の国際的な孤立や外交政策への不満も、軍部の不満をさらに助長しました。
こうした社会的な不安と政治不信の中で、若手将校たちは「日本を救う」という使命感を持ち、暴力的な行動に踏み切ることを決意したのです。
なお、満州事変については以下の記事で詳しく解説しています。
満州事変とは?分かりやすく解説|いつ、どのように起きたか、そのきっかけと結果
犬養毅首相暗殺の経緯とその最期の言葉
五・一五事件で犬養首相は暗殺されました。撃たれる際に狙撃者に向かって言った言葉、「撃つのはいつでも撃てる。まず話そう。話せばわかる。」でした。それはどういう意図だったのか、暗殺の経緯とその最期の言葉の意味を考えます。
犬養毅はなぜ暗殺されたのか?
犬養毅が暗殺された理由は、彼が立憲政治を重視する姿勢を貫いていたためです。

犬養は、当時の日本において、軍部の勢力拡大や強硬な外交政策に対して慎重な立場を取り、内政では浜口雄幸内閣が行った金解禁政策の見直しをして経済政策の立て直しに尽力していました。
また、犬養は軍部が進める対外侵略路線に対しても一定の抑制を試みており、この姿勢が軍部や右翼団体にとっては「国家の障害」と見なされ、「統帥権干犯である」と批判されていました。
特に、満州事変後の強硬外交を支持する軍部にとって、犬養の穏健な外交方針は容認できないものでした。その結果、犬養は軍部から目の敵にされ、ついには暗殺されるに至ったのです。
なお、浜口雄幸については以下の記事で詳しく解説しています。
内閣総理大臣・浜口雄幸の生涯と政治活動:東京駅での暗殺の背景、金解禁政策の効果を解説
「話せばわかる」とは?犬養毅の最後の言葉
5月15日、首相官邸を襲撃した若手将校らのなかでまず3名が犬養毅のいる部屋に乱入しました。
将校たちが官邸に乱入した際、犬養は冷静に彼らを迎え、ソファーに腰掛けて説得を試みました。この時に発せられたとされるのが、「話せばわかる」という言葉です。
この言葉は、犬養が最後まで暴力ではなく対話による問題解決を信じていたことを象徴しています。
しかし、その直後にさらに4名の将校らが乱入し、即座に犬養に向かって発砲。犬養は頭に被弾。これが致命傷となりました。
将校たちは犬養の説得に耳を貸さず、最終的に彼を射殺したことになります。
なお、犬養がこの言葉を本当に発したかどうかには諸説がありますが、後世においては立憲政治の象徴的なエピソードとして広く語り継がれています。
犬養の死は日本国内に大きな衝撃を与え、立憲政治の終焉を象徴する出来事として歴史に刻まれました。そして、その後の日本は軍部の支配が一層強まり、軍国主義への道を突き進むことになります。
五・一五事件に関与した人物とその役割
1932年5月15日に発生した五・一五事件では、多くの海軍青年将校や民間の右翼団体が中心となり、当時の内閣総理大臣・犬養毅以外にも何名かが襲撃を受けています。
この事件に関与した人物たちの思想や目的、そしてその後の人生を詳しく見ていきます。
なお、犬養毅については以下の記事で詳しく解説しています。
犬養毅とは何をした人か?憲政の神様としての生涯と業績、五一五事件暗殺の経緯とその最後の言葉まで徹底解説
五一五事件の首謀者の海軍将校とその役割
五・一五事件は、海軍の青年将校を中心に計画されました。主に、彼らは経済的不況と政党政治の腐敗に不満を持ち、「昭和維新」を掲げて政治体制の変革を図りました。
三上卓(みかみ たかし)
- 役割:首謀者の一人。事件当時、海軍中尉。
- 思想・目的:三上は国家改造を強く望んでおり、現状の政党政治を「腐敗」とみなしていました。特に、貧困層の救済と日本の「再生」を掲げていました。
- 事件後:事件後に逮捕され、軍法会議で懲役15年の判決を受けました。しかし、世論からの減刑嘆願により、1936年に恩赦で釈放されました。その後は政界に戻ることなく、政治的活動から離れました。
古賀清志(こが きよし)
- 役割:三上とともに、首相官邸襲撃の実行犯。事件当時、海軍少尉。
- 思想・目的:古賀も「昭和維新」に共鳴しており、武力行使によって国家を改造することが必要と考えていました。
- 事件後:軍法会議で懲役15年の判決を受けましたが、1934年に釈放されました。その後は軍からも退き、静かに暮らしました。
五一五事件の民間の関係者とその役割
五・一五事件には、右翼団体や農民団体の関係者も関与しました。関与した民間人は、当時の貧富の格差や社会的不平等に憤りを感じており、青年将校らと手を組んで行動しました。
井上日召(いのうえ にっしょう)
- 役割:右翼団体「血盟団」の指導者として事件の思想的支柱となった。
- 思想・目的:天皇親政を理想とし、現代の政党政治を排除しようとしました。
- 事件後:井上は五・一五事件の影響で警察に逮捕され、長期間の刑務所生活を送ったものの、戦後は右翼活動を再開しました。
五一五事件の被害者とその後の影響
五一五事件で襲撃された被害者と、事件後の影響について以下にまとめました。
犬養毅 – 内閣総理大臣
- 被害内容:海軍青年将校らによって首相官邸で銃撃され、暗殺されました。
- 影響:犬養の死により、政党政治は崩壊し、軍部の発言力が急速に増大しました。これにより、日本は徐々に軍国主義体制へと進んでいきます。
犬養毅以外の被害者
- 住友銀行本店襲撃:住友財閥は資本主義の象徴と見なされ、襲撃を受けましたが、人的被害はありませんでした。
- 警視庁襲撃:武力による政治介入を象徴するため、警察も標的となりました。
事件後の関与者たちの人生
五・一五事件後、多くの関与者は軍法会議で裁かれました。しかし、事件に対する世論は必ずしも厳しいものではなく、むしろ「腐敗した政党政治への挑戦」として同情的な声が多く上がりました。
そのため、短期間の服役で釈放され、事件後は政治的活動から手を引く者も多かったのです。
減刑の背景
当時の日本は軍国主義に傾倒しつつあり、青年将校たちの行動が一定の共感を呼んだことが影響しました。
結果として、多くの関与者が短期間で釈放され、その後は民間で静かに生活を送るか、戦争の影響で再び軍事に関与することもありました。
五・一五事件と新聞報道
五・一五事件を当時のメディアはどのように報じたのでしょうか。いくつかの資料の内容をまとめました。
事件後の新聞報道と世論の動き
1932年の五・一五事件が発生した直後、新聞各紙は事件を大々的に報じました。多くの新聞は、事件の背景にある軍部の若手将校らの不満に焦点を当て、事件を「義挙」とする同情的な論調を展開しました。
「義挙」という言葉は、政府や財界の腐敗を正すために行われた正義の行動として事件を位置づけ、将校たちの行動をある種の愛国的な行為と見なすものでした。
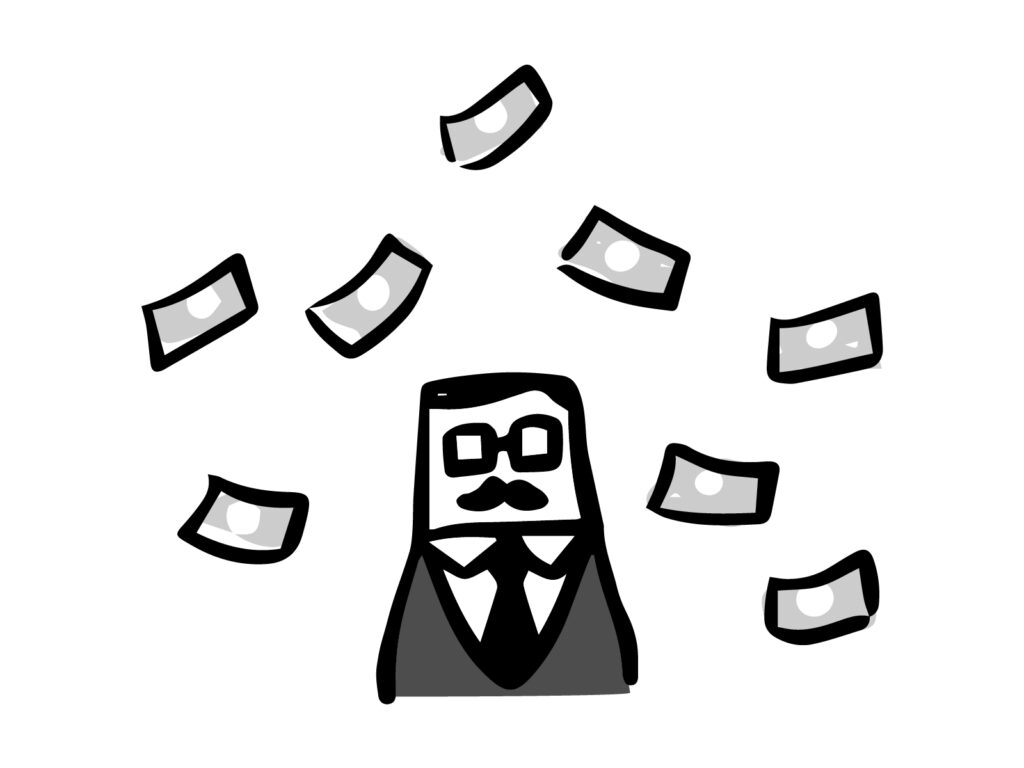
当時、国民の間でも政治不信が広がっていたため、新聞報道は世論に影響を与え、「政治家よりも軍部のほうが国家のために行動している」という見方が広まりました。結果として、軍部への支持が高まり、軍部の政治的な立場が一層強固なものとなっていきました。
一方で、立憲政治を擁護する声は次第に弱まり、民主主義が後退するきっかけにもなりました。
事件当時の新聞報道とその影響
五・一五事件が発生した1932年当時、日本の新聞は事件を大きく取り上げました。

多くのメディアは、事件を「義挙」(正義の行動)として報じました。これにはいくつかの理由があります。
- 当時の政党政治に対する不信感:国民の間では、経済不況や政党政治の腐敗に対する不満が高まっていました。メディアもこれに共鳴し、事件を既存の政治体制に対する「正義の行動」として報じることで、共感を得やすかったのです。
- 青年将校への同情:五・一五事件を起こした青年将校たちは、国家の未来を憂い、腐敗した政治を正そうとしたと説明されました。このため、彼らの行動が正当化され、国民の間に同情の声が広がりました。
一方で、政界ではこの報道が軍部の政治的影響力を増大させる結果となり、後の二・二六事件(1936年)への道を開く一因となりました。
ラジオ報道とその限界
当時、日本ではラジオ放送が徐々に普及していましたが、新聞に比べて報道内容は政府の監視下にありました。
ラジオ放送は、事件を詳細に伝えるよりも、政府の公式見解に基づく情報を配信することにとどまりました。そのため、ラジオの報道は政府寄りの情報が多く、青年将校たちの動機や事件の背景を深く伝えることはありませんでした。
事件後の報道規制とメディア統制
五・一五事件後、日本政府は軍部の政治的影響力が高まる中で、報道規制を強化しました。これは、同様の武力行使を煽動する可能性を排除するためでもありました。具体的には以下のとおりです。
- 軍部批判の抑制:事件後、軍部を批判する記事は次第に減少し、代わりに軍部の行動を称賛する報道が増加しました。
- 思想統制の強化:日本のメディアは、国民統制のためのツールとして活用されるようになり、自由な報道は次第に制限されました。
メディアの報道がもたらした影響
五・一五事件に対する新聞や雑誌などの報道は、軍部の台頭を助長する重要な役割を果たしました。事件を義挙として報じたことで、軍人たちが政治に関与することへの国民の心理的な抵抗感が薄れ、軍事政権に対する容認ムードが形成されました。
さらに、事件後の裁判においても、将校たちに対する処罰が軽減されたことが報道されると、「軍部が正義である」という認識が強まりました。
この流れは、1936年に発生する二・二六事件にも影響を与えました。二・二六事件は、軍部がさらに大胆に政治を掌握しようとする試みであり、五・一五事件の影響が根強く残っていたことが一因です。
結果的に、メディアの報道が軍部の権力を拡大させ、民主主義の後退を招いたのです。
五・一五事件後の政治的影響
五・一五事件がその後の日本の政治体制に大きな影響を与えました。
五・一五事件後に行われた裁判と判決
五・一五事件に関与した青年将校たちに対する裁判は、軍事法廷ではなく通常の民間の裁判所で行われました。この裁判は、事件発生の翌年である1933年に開かれましたが、判決は意外にも比較的軽いものでした。

判決の内容とその背景
- 主犯の青年将校たちは、禁錮15年から無期懲役という比較的軽い判決を受けました。
- 一部の実行犯は数年で仮釈放されることとなり、社会的な批判を浴びました。
このような軽い判決が下された背景には、以下の要因がありました。
- 世論の同情:多くの国民が、青年将校たちの行動を「腐敗した政党政治を正そうとする義挙」として肯定的に捉えていました。メディアもこの見方を後押しし、裁判における厳罰を求める声は少なかったのです。
- 軍部の圧力:軍部は裁判に影響力を行使し、将校たちが厳罰に処されることを防ぎました。軍内部では、彼らを国家の英雄視する意見もあり、軍部の権威を守るための動きがあったとされています。
事件後の政党解散と軍部の台頭
五・一五事件後、日本の政治は大きな転換点を迎えました。立憲政治の崩壊と軍部の台頭が急速に進行し、戦前の日本は徐々に軍国主義へと傾斜していきました。
時系列で見る政治的変化
- 1932年(五・一五事件発生):
犬養毅首相が暗殺され、政党内閣が崩壊しました。後任には、**斎藤実(さいとう まこと)**が内閣総理大臣に就任しましたが、彼は軍部と協調する形で政治運営を行い、政党の力は大きく後退しました。 - 1934年:
政党が軍部の政策に対する発言力をほとんど失い、軍部の発言力が一層強化されました。軍部は、政治だけでなく経済政策や外交政策にも大きな影響力を行使するようになります。 - 1935年~1936年(昭和11年):
軍部の中で、さらに急進的な勢力が台頭し、これが二・二六事件へとつながります。
立憲政治の終焉
五・一五事件をきっかけに、明治憲法下での立憲政治は終焉を迎えました。
以下のような変化が起こりました。
- 議会政治の形骸化:政党の影響力が弱体化し、内閣は軍部との協調を優先するようになりました。
- 軍国主義体制の確立:軍部が政府内で政策決定権を握り、軍事的拡張主義が国策として推進されるようになりました。
- 外交政策の硬化:軍部の主導によって日本の外交政策は強硬路線に転じ、中国や他国との軍事衝突が増加しました。
二・二六事件への影響と日本社会の変化
海軍青年将校らによる五・一五事件のわずか4年後(1936年に)、今度は陸軍青年将校らが二・二六事件を起こします。
五・一五事件から二・二六事件までの道のり
五・一五事件をきっかけに、軍部は政治への影響力をさらに強めていきました。
1930年代初頭の日本は、世界恐慌の影響で経済が低迷し、国民の不満が高まっていました。五・一五事件で政治家が暗殺された後、軍部はその不満を利用し、「強力な指導者による国家の再建」を掲げて支持を集めました。
1936年、若手陸軍将校たちが二・二六事件を引き起こしました。この事件は、軍部によるさらなるクーデターであり、政府要人を暗殺し、軍事政権の樹立を目指したものです。
二・二六事件は、五・一五事件と同様に「腐敗した政治を正す」との名目で行われ、国民の一部からは支持を受けましたが、政府の強硬な対応により失敗に終わりました。
しかし、この一連の流れによって、軍部が事実上の政治的支配者として台頭することとなり、立憲政治は崩壊への道を歩み始めました。

事件後の日本社会と立憲政治の終焉
二・二六事件を境に、日本は軍国主義への道を突き進むことになります。軍部は政治を完全に掌握し、内閣や国会における議論は形骸化しました。特に、昭和天皇が事件後に軍部の要求を容認する姿勢を見せたことで、軍部は政府内で絶対的な権力を持つようになりました。
また、メディアも軍部の影響下に置かれ、自由な言論は制限されるようになりました。新聞やラジオなどのメディアは、政府の検閲を受け、戦争賛美や軍事行動を正当化する報道を行うようになったのです。
このようにして、五・一五事件から二・二六事件を経て、日本社会は立憲政治から軍国主義体制へと大きく変化し、やがて日中戦争や太平洋戦争へと突き進んでいくことになります。
五・一五事件が日本の文化に与えた影響
五・一五事件は現代にいたるまで、何度も映画やドラマ、小説などで題材になっています。
映画・ドラマでの描かれ方
五・一五事件は、日本の映画やドラマでも度々取り上げられています。特に、軍部の台頭と政党政治の崩壊というテーマは、日本の近代史を語る上で重要な題材となっています。
- 映画『日本のいちばん長い日』(1967年)
この映画では、軍部が日本の政治にどのように影響を与えたかが描かれており、五・一五事件の背景やその後の影響も取り上げられています。 - ドラマ『坂の上の雲』(2009年)
この作品では、明治から昭和初期にかけての日本の社会変革が描かれ、五・一五事件がその象徴的な出来事として扱われています。
文学作品での描かれ方
文学の世界でも、五・一五事件は国家と個人の関係や軍部の権力拡大を描く作品の題材となっています。
- 三島由紀夫『憂国』
この作品では、国家への忠誠心と個人の葛藤が描かれており、五・一五事件や二・二六事件を背景に、武士道精神と現代日本の政治的変化が対比されています。

花ざかりの森・憂国 (新潮文庫)
現代の日本における五・一五事件の記憶
現代の日本において、五・一五事件は立憲政治が終焉を迎えた象徴的な事件として記憶されています。特に、以下の点で振り返る意義が強調されています。
- 民主主義と軍国主義の転換点:五・一五事件は、政党政治から軍国主義への移行を示す重要な出来事であり、現代の民主主義社会においても、政治と軍事の関係を考える際に重要な教訓を与えています。
- 自由と報道の意義:事件後に強化された報道統制や思想統制は、現代社会における表現の自由の重要性を改めて考えさせるものです。
事件を振り返る意義
五・一五事件を振り返ることは、単に過去の歴史を知るだけでなく、現代社会における政治と軍事のバランスや、報道の自由、さらには民主主義の脆弱性についても考える契機となります。
特に、軍部の台頭や政治的暴力がどのように社会を変えていくのかを学ぶことで、現代の日本が直面する課題への理解を深めることができます。
五・一五事件と二・二六事件の比較
五・一五事件と二・二六事件を比較すると、以下の表のようになります。
| 項目 | 五・一五事件 | 二・二六事件 |
| 発生年 | 1932年(昭和7年) | 1936年(昭和11年) |
| 首謀者 | 海軍青年将校 | 陸軍青年将校(皇道派) |
| 目的 | 政党政治の打倒と国家改造 | 皇道派による軍事政権の樹立 |
| ターゲット | 政治家(犬養毅首相) | 政治家および陸軍上層部 |
| 結果 | 犬養毅首相が暗殺され、軍部が台頭 | クーデターは失敗、首謀者は処刑 |
共通点と相違点について、以下にまとめました。
共通点と相違点
共通点
- 軍部内の不満:両事件ともに、軍部内の不満が引き金となり、現状の政治体制に対する不満が背景にありました。特に、既存の政党政治が腐敗していると認識されていました。
- 国民の同情:五・一五事件では国民の同情が大きな役割を果たしましたが、二・二六事件でも一部の国民や軍部内での同情的な見方がありました。
相違点
- 成功と失敗:五・一五事件では、首相暗殺を含む計画が成功しましたが、二・二六事件はクーデターとしては失敗に終わりました。
- 事件後の対応:五・一五事件後は比較的軽い判決が下された一方、二・二六事件では厳しい処罰が行われ、関与者の多くが処刑されました。
両事件で日本が軍国主義化していく経緯
五・一五事件がきっかけとなり、軍部は政治への影響力を大幅に強化しました。政党政治が弱体化し、軍部が政策決定の中枢に進出しました。
二・二六事件の失敗後、陸軍内の急進派は排除されましたが、これにより統制派(軍の中でも穏健派)が軍事政権を主導する形となり、さらに軍国主義が強化されました。
事件後の日本社会の変化
五・一五事件、そして二・二六事件につづいて1937年には日中戦争が勃発。軍国主義が国策として完全に定着しました。国民は、軍事教練や戦時体制への協力を求められるようになり、社会全体が戦争に向かって動き始めました。
五・一五事件から二・二六事件を経て、戦前の日本は議会政治から全体主義国家へと転換、大正時代の護憲運動もむなしく、自由と民主主義が失われていく時代に突入しました。
なお、護憲運動については以下の記事でくわしく解説しています。
護憲運動とは?大正デモクラシーを象徴する民主化運動の背景と影響を解説
五・一五事件に関するQ&A
五・一五事件とは何ですか?
A:
五・一五事件は、1932年5月15日に発生した、日本の若手海軍将校らが首相・犬養毅を暗殺したクーデター事件です。東京市内で複数の襲撃が行われ、政財界に大きな衝撃を与えました。この事件は、日本の立憲政治が軍部の台頭によって崩れ始めた重要な転機とされています。
五・一五事件はいつ、どこで起きましたか?
A:
事件は1932年5月15日に、東京の首相官邸で発生しました。この日、若手海軍将校たちは首相官邸に押し入り、当時の首相である犬養毅を襲撃し、射殺しました。
なぜ五・一五事件は起きたのですか?
A:
五・一五事件の背景には、以下の要因があります。
犬養毅首相はなぜ暗殺されたのですか?
A:
犬養毅は、立憲政治と自由主義を重視し、軍部の政治介入に対して慎重な姿勢をとっていました。しかし、これが軍部にとっては政治の変革を妨げる存在と見なされ、襲撃の標的になりました。犬養の暗殺は、軍部による政治支配への第一歩となりました。
「話せばわかる」という犬養毅の最後の言葉とは?
A:
事件当日、犬養毅は将校たちを説得しようとし、「話せばわかる」と語りかけました。しかし、将校たちは犬養の言葉を聞き入れず、最終的に犬養を射殺しました。この言葉は、犬養の立憲政治と対話による解決を信じた姿勢を象徴するものとして広く知られています。
五・一五事件を当時の新聞はどう報道した?
A:
事件後、新聞各紙はこのクーデターを「義挙」として同情的に報じました。多くの報道が、腐敗した政党政治を正す行動として将校たちを擁護する内容でした。これにより、国民の間でも軍部の支持が高まり、軍部が政治に介入することへの抵抗感が薄れていきました。
五・一五事件は二・二六事件にどのような影響を与えましたか?
A:
五・一五事件は、軍部が政治に介入するきっかけとなり、その後の二・二六事件(1936年)に直接つながりました。五・一五事件での軍部の行動がある程度容認されたことで、陸軍の若手将校たちはさらなるクーデターを計画し、政府の要人を暗殺して軍事政権を樹立しようとしました。
五・一五事件後、日本社会はどう変わりましたか?
A:
五・一五事件後、日本は急速に軍国主義化へと進んでいきました。立憲政治は事実上崩壊し、軍部が国家を支配するようになります。また、自由な言論や報道も制限され、戦争への準備が進められていきました。この流れは、日中戦争(1937年)や太平洋戦争(1941年)へとつながっていきます。
まとめ
五・一五事件は、犬養毅首相暗殺という衝撃的な出来事を通じて、日本の立憲政治が崩壊し、軍部が台頭する時代の幕開けとなりました。
事件後の新聞報道や国民の反応は、軍部のクーデターを肯定する空気を醸成し、後の二・二六事件や太平洋戦争へとつながります。
この事件は、日本の近代史を語る上で重要な転換点であり、現代においてもその教訓が語り継がれています。
【参考】
国立公文書館
函館市/函館市地域史料アーカイブ
WEB歴史街道
公益社団法人 國民会館
現代メディア
プレジデントオンライン



コメント