現在、日本の国政選挙では「投票所」に行く方法での投票が求められています。商品の注文や配達、ホテルや新幹線の予約、役所の事務作業すらもネットでできるのに、なぜネットで投票できないのでしょうか。
これには理由があります。その理由をまとめて紹介し、海外でのネット投票の事例も紹介します。
※関連記事:選挙権18歳:18歳以上に引き下げられた理由とその影響、被選挙権の年齢引き下げに関する議論をまとめました
ネット投票の基本情報

ネット投票とは、インターネットを利用して投票を行う仕組みを指します。従来の紙や投票所での投票に代わり、自宅やどこからでもオンラインで投票できることが特徴です。
近年、選挙制度改革の一環として、導入が議論されています。
注目される背景
- 投票率の低迷:特に若者の投票率を改善するための手段として期待されている。
- テクノロジーの進化:ブロックチェーン技術やデジタルセキュリティの進展により、実現可能性が高まっている。
- コロナ禍での非接触ニーズ:パンデミックをきっかけに、リモートでの投票の重要性が再認識された。
ネット投票の仕組み:導入に必要な技術とその手順
ネット投票は、選挙管理システムと有権者のデバイスを連携させて行われます。この仕組みを安全かつ効率的に実現するためには、以下の技術が不可欠です。
必要な技術と機能
- 本人認証システム:マイナンバーカードや生体認証を活用し、なりすましを防止。
- 投票データの暗号化:ブロックチェーン技術により改ざんや不正アクセスを防ぐ。
- 投票結果の匿名性の確保:投票者のプライバシーを守りながら正確な集計を実施。
投票手順の概要
- ログイン:事前に登録されたIDやパスワードで専用ポータルにアクセス。
- 本人確認:顔認証やパスコード入力を通じて本人確認を実施。
- 投票操作:画面上の候補者名や政党名を選択して送信ボタンを押す。
- 確認と完了:投票内容を確認後、暗号化された形で送信が完了。
日本でネット投票が実現しない理由

インターネットが普及して以降、選挙でネット投票ができるようにしようという議論が行われています。
2013年には議員立法により、インターネットを使った選挙運動が解禁されました。2024年の東京都知事選では候補者がSNSを活用した選挙運動を展開して事前予想を大きく票を上回るサプライズも起きました。
参考:Yahoo!ニュース「東京都知事選2024でネットはどのように使われていたか」
ところが、ネット投票はいまだに実現していません。
これにはいくつか理由があると言われています。
与党が選挙に負けないようにするため
1つ目の理由は、与党による「選挙対策」です。
ネット投票が解禁されると、「それまで投票していなかった層」が投票行動を起こすと考えられています。すると、その層が支持しない政党は不利になります。
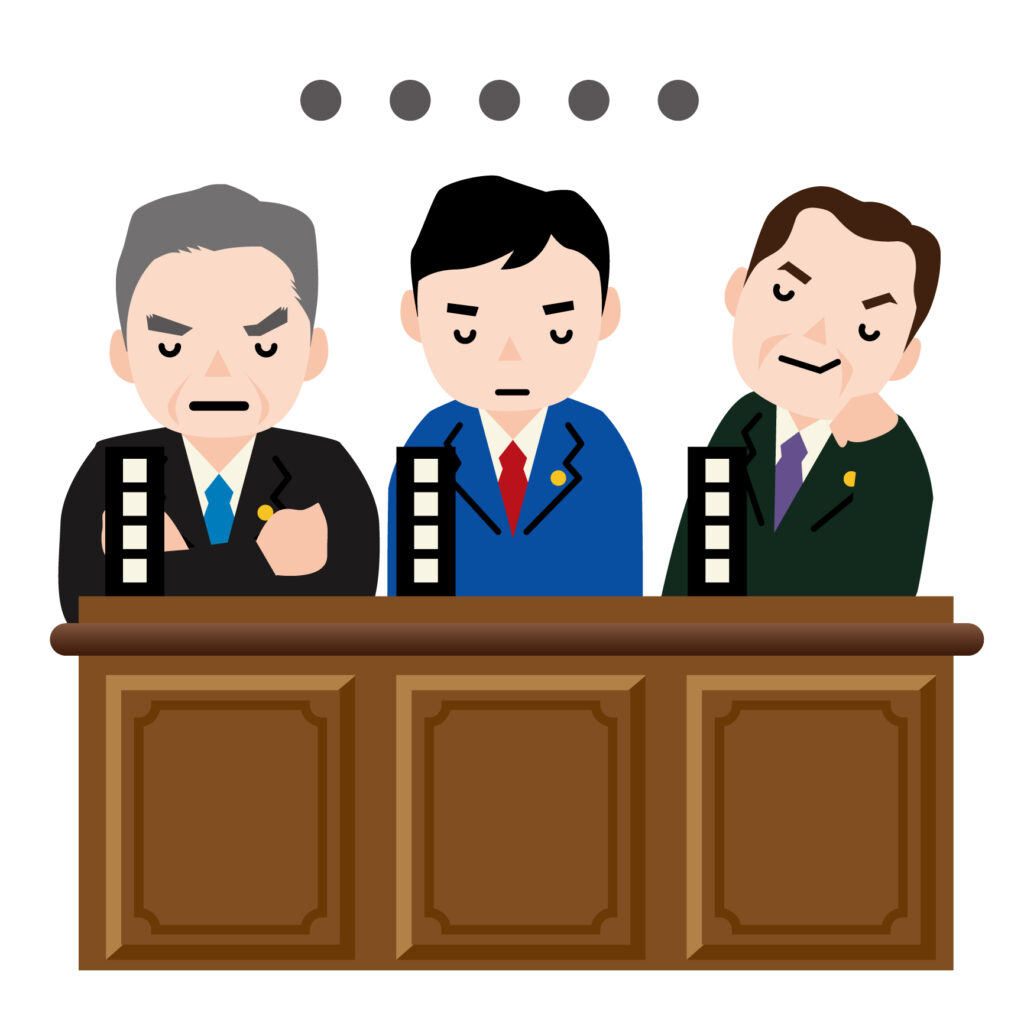
若い世代の投票率は低い
以下は、年代別の投票率です。10代~30代の投票率は30~40%台で、40代以上の世代より投票率が低いです。
| 10歳代(%) | 20歳代(%) | 30歳代(%) | 40歳代(%) | 50歳代(%) | 60歳代(%) | 70歳代以上(%) | 全体(%) | |
| 2016年 参議院選挙 | 46.78 | 35.60 | 44.24 | 52.64 | 63.25 | 70.07 | 60.98 | 54.70 |
| 2017年 衆議院選挙 | 40.49 | 33.85 | 44.75 | 53.52 | 63.32 | 72.04 | 60.94 | 53.68 |
| 2019年 参議院選挙 | 32.28 | 30.96 | 38.78 | 45.99 | 55.43 | 63.58 | 56.31 | 48.80 |
| 2021年 衆議院選挙 | 43.23 | 36.50 | 47.13 | 55.56 | 62.96 | 71.38 | 61.90 | 55.93 |
| 2022年 参議院選挙 | 35.42 | 33.99 | 44.80 | 50.76 | 57.33 | 65.69 | 55.72 | 52.05 |
自民党が若い世代にあまり支持されていない
2024年5月時点のNHKの世論調査では、自民党の支持率は全世代をつうじて27.5%でした。
世代別にみると、18歳~39歳は16.8%と、全世代を通じて最も支持率が低いです。
ネット投票の解禁によって「自民党支持者の少ない層」が新たに投票するようになると、自民党が選挙で負ける危険性が高まります。
これがネット投票実現をはばむ原因のひとつとされています。
これに対して立憲民主党と日本維新の会は2023年、「インターネット投票の導入の推進に関する法律案」を共同提出しています(衆議院・第211回国会提出法案より)。

ネット投票の潜在リスクが大きいため
2つ目の理由は技術的な問題です。ネット投票にはさまざまなリスクがあり、それを「完全に」解決する手段がない、というのが理由です。
例えば以下のようなリスクが考えられています。
- 投票のなりすまし
- アカウントの乗っ取り
- 投票結果のデータ改ざん
- システム障害
ネット投票をはじめるとすると、有権者1人ひとりに投票IDが割り当てられるとされています。そのIDを不正に取得すると、本人になりすまして特定の候補者に投票することが可能です。
例えば老人ホームに入居している高齢有権者になりすまして職員などが不正投票することも、技術的にはむずかしくないでしょう。
同様に、有権者ごとにアカウントを作成しても、そのアカウントを乗っ取れば不正投票ができます。
さらに、公正に投票されたとしても、サイバー攻撃によって投票結果を改ざんされる恐れもあります。
紙の投票用紙であれば用紙をみてもう一度集計できます。ですが、データだと改ざん前の結果(どの候補者に投票したか)を調べるのが技術的にむずかしい場合も考えられます。
また、サーバーがダウンするなどシステム障害が発生するケースも考えられます。選挙に限らず、定期的にどの企業、どの地域でも発生しています。投票中にシステム障害が発生する可能性は必ずあると言えるでしょう。
ネット投票のリスクへの対処法
では、前述のような「ネット投票の技術的リスク」を回避する方法はないのでしょうか。
いくつか提案されている方法があるので、まとめてみました。
参考:総務省「在外選挙インターネット投票システムの技術的検証及び運用等に係る調査研究事業」
出口調査の結果と照らし合わせる
投票に不正操作があったかどうかの判断基準のひとつとして、出口調査の結果を採用すれば良いという考えがあります。
出口調査は選挙当日、投票を終えた有権者を対象に投票所の出口で投票先などを聞く調査です。かなり信頼性の高い調査であり、実際、出口調査の結果で開票作業「前」に当選確定が分かる場合すらあります(岡山理科大学などより)。
選挙結果と出口調査の結果が大きく異なっていれば、何らかの不正操作が行われた可能性があります。疑惑があると分かれば、「何らかの対応が必要だ」という説得力が生まれ、必要な対応を取りやすくなります。
投票のやり直しを可能にする
投票のなりすましやデータ改ざんが行われると、出口調査などの結果と大きく異なる投票結果が出る可能性があります。
そんなときに投票のやりなおしをすれば良いという意見もあります。
現在の公職選挙法では投票のやり直しができません。たとえ選挙管理委員会の案内ミスだったとしてもやり直しできないようになっており、過去にそれが原因でトラブルになった例もあります(朝日新聞など)。
法律を改正して一定の場合に投票のやり直しを認めれば、ネット投票のリスクにある程度対処できます。
システム障害に対応できるシステムをつくる
システム障害のリスクに対しては、事前に対応できるような仕組みやシステムを構築しておけば、かなりの程度予防できるはずです。
そもそもシステム障害の原因は「ハードウエア障害」「ソフトウエア障害」「人的ミス」の3つと言われています。日々のメンテナンス、バグ対応、人的ミスを防ぐ二重三重のチェック機能などで大部分は予防できます。
とはいえ、KDDIやみずほ銀行のような大障害が起こったケースもあります。これについては、「リスクをゼロにする」のはほぼ不可能かもしれません。
海外でのネット投票の状況
ネット投票が技術的に可能になって以降も、国政選挙でネット投票を実施している国は海外でもほとんどありません。
エストニアのネット投票例
実は、ネット投票を実現させているのは、OECDに加盟している38か国のなかではエストニアだけです。
エストニアでは2007年の国政選挙からネット投票がはじまっています。すると、それ以前は議席率が2割に満たない第三党に過ぎなかったエストニア改革党(Reformerakond)が議席数を2倍近くに伸ばして第一党に躍進。以降も30-40%近い議席率を維持して第一党として首相を輩出しています。
このように、ネット投票をはじめるとそれまでの選挙結果がガラリと変わる可能性を秘めているのです。
ネット投票のメリット
日本含めて海外でもほとんど全面採用に至っていないネット投票。それでも解禁の声がなくならないのは大きなメリットがいくつもあるからです。
若い世代も投票しやすくなる
そのうちのひとつは「若い世代の政治参加」です。
日本では10代~30代の投票率が30~40%台と、ほかの先進国と比べて極めて低いです。若者など特定の世代の政治への意識がうすれていくと、必要な社会保障制度改革や弱者救済、経済力アップなどさまざまな面で進歩が遅れたり、偏ったりしていきます。
「24時間投票可能」「自宅で投票可能」「スマホで投票可能」のような便利なシステムを導入すれば、現在投票していない人たちにも投票をうながし、政治への意識を高めていける可能性があります。
実際、若い世代の政治参加をうながすために選挙権が与えられる年齢も海外同様に18歳以上に引き上げられています。
なお、選挙権が18歳以上に引き下げられた経緯や影響について、以下の記事で詳しく解説しています。
選挙権18歳:18歳以上に引き下げられた理由とその影響、被選挙権の年齢引き下げに関する議論をまとめました
開票作業が瞬時に終わる
ネット投票がはじまると、開票作業が瞬時に終わるかもしれません。
現在は投票箱をあけて1枚1枚開票して集計しているため、開票作業に何時間もかかっています。ですが、ネット投票であれば集計作業は一瞬で終わります。
また、2017年の衆議院選挙では台風の影響で投票所に投票箱が届かず、開票作業が大幅に遅れる事態も発生しました。この経験から、ネット投票が政権内でも議論されたこともありました(NHK・政治マガジン「ネット投票 なぜできない」より)。
投開票の費用を削減できる
ネット投票が一般的になると、投開票にかかわる費用を大幅に削減できます。
現在、国政選挙の投開票には556億円かかっているそうです(鳥取県「選挙に係る経費は?」より)。この費用には投票所にかかる経費、開票所にかかる経費などがあります。
ネット投票が広まればこうした費用の多くを削減でき、社会保障などに回すことも可能になるでしょう。
ネット投票のメリットとデメリットまとめ
ネット投票には、投票率向上や利便性向上といった利点がある一方、セキュリティリスクや不正投票の懸念も指摘されています。それぞれの特徴を以下にまとめます。
メリット
- 投票率の向上:移動が困難な人や若者の参加率が上がる可能性が高い。
- コスト削減:紙や投票所設営にかかる費用を大幅に削減できる。
- 時間的な柔軟性:24時間いつでもどこでも投票可能。
デメリット
- サイバーセキュリティリスク:ハッキングやデータ漏洩の可能性がある。
- 不正投票の懸念:本人確認が適切に行われない場合、複数投票のリスクが高まる。
- デジタル格差の問題:高齢者やITリテラシーが低い層が参加しづらくなる可能性。
ネット投票に関するQ&A
Q1. ネット投票とは何ですか?
ネット投票とは、インターネットを活用して自宅や任意の場所から投票を行うシステムです。紙や投票所での従来の方法に代わり、オンラインで投票手続きを完了できます。
Q2. ネット投票が注目されている理由は何ですか?
- 投票率の向上:若者や高齢者など、移動が難しい人々の投票参加が期待されています。
- コロナ禍の影響:非接触での投票が求められた背景があります。
- コスト削減:紙や投票所設営費を削減できる可能性があります。
Q3. ネット投票の仕組みはどのようなものですか?
- 有権者が専用ポータルにアクセスしてログイン。
- 生体認証やマイナンバーカードを使用して本人確認を実施。
- 投票画面で候補者を選び、内容確認後に送信。
- 投票データは暗号化され、匿名性が確保されます。
Q4. ネット投票のメリットとデメリットを教えてください。
メリット
- 時間や場所に縛られずに投票可能。
- 投票率の向上が期待できる。
- 投票にかかる費用を削減可能。
デメリット
- ハッキングやデータ改ざんのリスク。
- ITに不慣れな層への対応が必要。
- 公職選挙法の改正など法整備が必要。
Q5. 日本ではネット投票は導入されていますか?
現時点では日本国内の選挙で正式に導入されていません。一部の自治体で試験導入が行われていますが、全国的な導入には至っていません。
Q6. 世界でネット投票を導入している国はどこですか?
- エストニア:世界初のネット投票を2005年に導入。全体の投票の50%以上がオンライン。
- アメリカ:一部州で軍人や海外在住者向けに採用。
- スイス:試行の結果、安全性の問題で一部撤回されました。
参考:swissinfo.ch
Q7. 日本でネット投票を導入するにはどのような課題がありますか?
- 技術的課題:不正アクセスや改ざんを防ぐシステムの構築。
- 法制度の整備:公職選挙法の改正が必要。
- 国民の信頼性確保:ネット投票の安全性や透明性への理解が求められる。
Q8. ネット投票が導入されることでどんな効果が期待されますか?
- 投票率の向上により、選挙がより多くの国民の意思を反映するものになる。
- 若者や忙しい世代が気軽に政治参加できるようになる。
- コスト削減による選挙運営の効率化。
Q9. ネット投票の安全性はどう担保されるのですか?
- 暗号化技術やブロックチェーンを活用して不正や改ざんを防止。
- 本人確認に生体認証やマイナンバーカードを活用し、なりすましを防ぐ。
- 投票データの匿名性を確保する仕組みを導入。
Q10. ネット投票は日本の選挙をどう変える可能性がありますか?
- 若者の投票率が向上し、政策に対する世代間のバランスが改善される。
- 地方や海外在住者の選挙参加が促進される。
- 新しい選挙文化の定着により、政治参加がより身近なものになるでしょう。
まとめ
日本の国政選挙でネット投票がはじまらない理由を紹介しました。
サイバー攻撃や投票のなりすまし、システム障害などのネット特有のリスクのほかに、エストニアで見られたように「選挙結果が大きく変わってしまう」というリスクも存在します。
ただ、これらの多くはネット社会では当たり前のことであり、ある程度までは対処法も実施されています。
ネット投票のメリットやリスクについて議論が進んでいくと良いですね。



コメント