選挙に立候補する際、法務省に供託金と呼ばれる現金あるいは国債証書を預けます。一定の得票数を獲得しないと没収されるお金です。
この記事では供託制度がどのような制度であり、供託金の没収ラインがどこなのか、また供託制度が機能しなかった例を紹介します。
選挙の供託金とは

国政選挙でも地方選挙でも、選挙に立候補する際に一定額の現金か国債証書を法務局に預けます。これを「供託金」と呼びます。
供託は、当選を争う意思のない人の売名目的などでの立候補を防ぐための制度です。
供託金の金額一覧
供託の金額は選挙の種類によって異なります。
| 選挙の種類 | 供託額 | 供託物が没収される得票数、またはその没収額 |
| 衆議院小選挙区 | 300万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
| 衆議院比例代表 | 候補者1名につき600万円 | 没収額=供託額―(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2) |
| 参議院比例代表 | 候補者1名につき600万円 | 没収額=供託額―600万円×比例代表の当選者数×2 |
| 参議院選挙区 | 300万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/8未満 |
| 都道府県知事 | 300万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
| 都道府県議会 | 60万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満 |
| 指定都市の長 | 240万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
| 指定都市議会 | 50万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満 |
| その他の市区の長 ※東京23区含む | 100万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
| その他の市区の議会 ※東京23区含む | 30万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満 |
| 町村長 | 50万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
| 町村議会 | 15万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満 |
供託金の没収ライン
選挙の種類ごとで細かく規定されていますが、要するに、有効投票の1割未満しか取れなければ供託金は没収されます。
供託金没収ラインの例

【衆議院議員総選挙の場合】
衆議院議員総選挙の供託金は300万円で、没収点は有効投票の10%未満です。
以下の場合、立候補者5名のうちDさんとEさんは供託金300万円が没収されます。
| 立候補者 | 得票数 | 有効得票率 |
| Aさん | 100,000 | 40% |
| Bさん | 80,000 | 32% |
| Cさん | 50,000 | 20% |
| Dさん | 12,000 | 4.8% |
| Eさん | 8,000 | 3.2% |
| 合計 | 250,000 | – |
【指定都市の市議会選挙の場合】
指定都市の市議会選挙の供託金は50万円です。例えば大阪市北区は定数4なので、没収点は有効投票数の2.5%未満です。
以下の場合、立候補者8名のうちHさんは供託金50万円が没収されます。
| 立候補者 | 得票数 | 有効得票率 |
| Aさん | 30,000 | 27% |
| Bさん | 25,000 | 23% |
| Cさん | 20,000 | 18% |
| Dさん | 10,000 | 9% |
| Eさん | 9,000 | 8% |
| Fさん | 7,500 | 7% |
| Gさん | 6,500 | 6% |
| Hさん | 2,000 | 2% |
| 合計 | 110,000 | – |
没収された供託金はどうなるのか
法定得票率に達しなかった場合、供託金は没収された。没収された供託金は、国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合は各地方自治体に帰属することになっています。
供託金の払い戻し方法
選挙終了から14日後に「供託原因消滅証明書」が届きます。この証明書と立候補の際に提出した「供託書正本」の2通を添付して法務省に「供託金払渡請求書」を提出すると、供託金が払い戻しされます。
供託金には利息がつく
実は、供託金には利息がつきます。法務省に預けている間にわずかですが、利息がつきます。
2019年より供託金利息は年0.0012%です(法務省HPより)。
過去の供託金額の変遷
選挙供託金制度に関する詳細な情報は、国立国会図書館の調査資料にまとめられています。過去の供託金額を表にまとめています。
| 制定年 | 衆議院 | 参議院 |
| 1925年 | 2千円 | – |
| 1947年 | 5千円 | 5千円 |
| 1948年 | 3万円+2万円 ※公営分担金:返還されないお金 | |
| 1950年 | 3万円+2万円 ※公営分担金:返還されないお金 | |
| 1952年 | 10万円 | 10万円 |
| 1962年 | 15万円 | 15万円 |
| 1969年 | 30万円 | 30万円 |
| 1975年 | 100万円 | 100万円 |
| 1982年 | 200万円 | 200万円 |
| 1992年 | 300万円 | 300万円 |
| 1994年 | 小選挙区:300万円 比例代表制:600万円 | 選挙区:300万円 比例代表制:600万円 |
日本と他国の供託金制度の比較
【参考】
法務省 供託制度に関する外国法制等の調査研究業務報告書
参議院
日本の供託金制度
日本では、国政選挙や地方選挙に立候補する際、一定額の供託金を納付する必要があります。この制度の目的は、無責任な立候補を抑制することにあります。供託金は選挙ごとに金額が異なりますが、次のように設定されています:
- 衆議院選挙(小選挙区):300万円
- 参議院選挙(比例代表):600万円
一定以上の得票率を獲得できない場合、供託金は没収されます。
日本の供託金は非常に高額で、世界的に見ても突出している点が特徴です。そのため、候補者にとって大きな経済的負担となり、特に若者や経済的に余裕のない人々にとって障壁になっています。
イギリスの供託金制度
イギリスでは、供託金の金額が日本と比較して非常に低く設定されています。
- 供託金:500ポンド(約9万5千円)
- 没収基準:有効投票総数の5%未満
この金額は1985年に設定され、比較的長期間変更されていません。供託金の没収基準も低く、候補者が供託金を回収しやすい仕組みになっています。
この制度の目的は、無意味な立候補を防ぎつつも、立候補のハードルを極力低く保つことにあります。
アメリカの選挙制度
アメリカでは、日本やイギリスのような供託金制度は存在せず、代わりに候補者が一定数の有権者から署名(候補者推薦署名)を集めることが求められます。
この方法は、立候補を金銭的な負担ではなく、支持者の数に基づいて決定する仕組みです。これにより、幅広い層が選挙に参加することを可能にしています。
ドイツの供託金制度
ドイツでは、供託金制度が存在しますが、日本ほど高額ではありません。
- 供託金:州ごとに異なるが、おおよそ300~500ユーロ程度(約4万5千円~7万5千円)
- 没収基準:有効投票総数の一定割合を獲得できなかった場合
また、政党に所属していない無所属の候補者に対して、推薦署名の提出を義務付けることで、立候補の真剣度を確認しています。
主要な違いの比較
| 国名 | 供託金額 | 没収基準 | 特徴 |
| 日本 | 300万~600万円 | 得票率が一定基準未満 | 非常に高額で立候補の障壁が高い |
| イギリス | 約9万5千円 | 有効投票総数の5%未満 | 負担が軽く、立候補しやすい |
| アメリカ | なし | なし | 推薦署名制度を採用し、金銭負担は不要 |
| ドイツ | 約4万5千円~7万5千円 | 得票率が一定基準未満 | 比較的低額で、推薦署名制度を併用 |
総評
日本の供託金制度は他国に比べて極めて高額であり、立候補のハードルが非常に高いことがわかります。
一方、イギリスやドイツでは負担を軽減しつつも制度の趣旨を保ち、アメリカでは金銭的負担を完全に排除したシステムを採用しています。
日本の制度が民主主義における多様性を制約しているとの指摘もあり、制度改革の議論が求められています。

供託金が高額になる理由の背景
選挙における供託金が高額になる背景には、いくつかの要因が存在します。その主な理由として、選挙費用の高騰と候補者の乱立を防ぐ目的が挙げられます。
選挙費用の高騰
日本の選挙は、ポスター作成や選挙カー、広報活動などに多額の費用がかかることで知られています。
選挙管理の運営費用を賄うために供託金が設定され、高額になる傾向があります。
また、供託金は、公共の場で行われる選挙活動のコストを補填する役割も果たしていると考えられています。
以下の記事で国会議員や地方議員になるのにいくら必要なのかを解説しています。
政治家になるには?必要な資格・学歴・経験と成功の秘訣や必要なお金を徹底解説!【国会議員編】
県会議員・市町村議員になるにはどうすればいいか?地方議員の多い政党や年収の実態を徹底解説!
候補者の乱立防止
供託金は、選挙における候補者数の乱立を抑制するための仕組みとして機能しています。供託金がなければ、名前を売るためだけに立候補する人が増え、選挙が混乱する可能性があります。
特に、供託金の没収制度が「一定以上の得票が得られない候補者の排除」を目的としている点が、その抑制効果を示しています。
供託金を支払えない候補者への影響
供託金制度は、資金的余裕がない候補者にとって大きな障壁となることが多く、無所属候補や若手候補者に特に不利に働きます。
無所属候補への影響
無所属の候補者は、政党の支援を受けられないため、供託金や選挙運動費用を自力で準備しなければなりません。そのため、金銭的な余裕がない場合には立候補を諦めざるを得なくなります。
これにより、幅広い意見が反映されるべき民主主義の本質が損なわれる恐れがあります。
なお、無所属と諸派の違いについて以下の記事で詳しく解説しています。
諸派とは何か?諸派のメリット・デメリット、存在意義、主要政党や無所属との違いを解説します
若手候補者への影響
若手候補者の場合、政治経験や人脈が少なく、資金調達が難しいケースが多いです。その結果、供託金のハードルが立候補への意欲を削ぎ、政治の世代交代や新しい視点の導入が妨げられる問題があります。
諸外国と比較して、日本は女性政治家の割合が極めて低いです。その原因のひとつに「費用の高額さ」も挙げられます。
特に地方選挙では、このような課題が顕著です。
なお、海外と日本の女性政治家の割合について、以下の記事で詳しく解説しています。
世界の女性議員の人数や割合(ランキング):日本は世界で何位?先進国(G7やOECD)のなかで何位?
供託金と選挙の公平性に関する議論
供託金制度は、民主主義における公平性の観点からも議論の的となっています。
公平性の欠如
供託金制度は、高額な金額を支払える経済的に恵まれた候補者に有利である一方で、資金力に乏しい候補者を排除する仕組みとして機能することがあります。
結果として、経済力に基づいて候補者が選別される構造が生まれ、真に有権者の意思を反映する選挙が実現しづらくなる可能性があります。
民主主義への影響
供託金制度は、候補者の経済的負担を重視するあまり、政治的な多様性を犠牲にするリスクがあります。多様な意見や立場を持つ候補者が立候補できない場合、民主主義の本質である「多様な意見の反映」が損なわれる恐れがあります。
そのため、供託金制度が民主主義の公平性をどのように確保すべきかについて議論が求められています。
なお、民主主義の歴史や重要性について以下の記事で詳しく解説しています。
民主主義の歴史と発展:ポピュリズム、エリート主義との関係をわかりやすく解説
代替案の模索
一部では、署名制度や候補者選出における新しい方法を導入することで、供託金制度の公平性を補完しようとする動きも見られます。
特に、他国の制度を参考にしながら、供託金の金額や没収基準の見直しが提案されています。
供託金制度が機能しなかった例
供託制度は、売名行為での立候補を抑制して健全な選挙を実施するための制度です。ですが、供託制度が機能せず、結果的に立候補者の大半が供託金を没収されたり、売名行為が疑われるような結果になった選挙がたびたび発生しています。
2022年参院選(富山選挙区)
2022年に行われた参院選富山選挙区では6名が立候補しました。結果は、自民党の現職・野上浩太郎氏が得票率68.77%で圧勝。次点の京谷公友氏(大阪維新・新人)ですら得票率9.80%という結果でした(朝日新聞デジタルより)。
参院選では有効投票の1/8以上取らないと供託金が没収されるため、当選した野上氏以外の全候補者が供託金を没収されるという事態になりました。
もちろん野上氏以外の候補者が売名行為だったというわけではなく、選挙戦略の失敗が原因とされています。
当選者以外が供託金没収という圧倒的な結果が出たことで、選挙戦略の練りなおしだけでなく供託制度の在り方にも一石が投じられることになりました。
2024年東京都知事選
2024年に行われた東京都知事選には史上最多の56名が立候補しました。掲示板の利用方法や政見放送でのパフォーマンスなど、さまざまな物議をかもした選挙になりました。
都知事選の供託金は300万円で、没収ラインは有効投票の10%です。
56名の立候補者のうち小池氏、石丸氏、蓮舫氏をのぞく53名が得票率10%に届かず、供託金合計1億5900万円が東京都の一般財源になりました。
売名行為を防ぐという供託制度が機能していないと疑われる顕著な例になってしまいました。
※関連記事:選挙ポスター デザイン:選挙に勝てるポスターや票を集めるデザインの特徴を紹介(キャッチコピー例付き)
供託金に関するQ&A
Q1. 供託金とは何ですか?
A1. 供託金は、選挙に立候補する際に候補者が支払う金銭です。一定以上の得票数を得られなかった場合、この供託金は没収されます。候補者数の乱立を防ぎ、選挙の公正な運営を目的としています。
Q2. 日本の供託金の金額はどのくらいですか?
A2. 日本の供託金は非常に高額で、衆議院小選挙区では300万円、比例代表では600万円、参議院選挙区では300万円、比例代表では600万円となっています。地方選挙も選挙ごとに金額が異なります。
Q3. なぜ日本の供託金は高額なのですか?
A3. 高額な理由として、選挙費用の高騰を補うためや、候補者の乱立を防ぐ目的が挙げられます。選挙活動には多大な費用がかかるため、供託金を通じて一部を補填する仕組みが取られています。
Q4. 供託金を支払えない場合、どうなりますか?
A4. 供託金を支払えない場合、候補者として立候補することができません。このため、無所属候補や若手候補者が特に不利な状況に置かれる場合があります。
Q5. 供託金制度にはどのような問題がありますか?
A5. 主な問題は、資金力がない候補者が立候補しづらい点です。結果として、多様な意見が反映されにくくなり、民主主義の公平性が損なわれる可能性があります。また、記載漏れや不透明な運用が発生することも課題です。
Q6. 他国にも供託金制度はありますか?
A6. 他国にも供託金制度を採用している例はありますが、日本ほど高額な場合は稀です。例えば、イギリスでは候補者が500ポンド(約10万円)を支払い、得票率が5%未満の場合に没収される制度があります。
Q7. 日本の供託金制度を改善する案はありますか?
A7. 供託金を引き下げる、あるいは署名制度を導入する案が議論されています。また、供託金の没収基準を緩和することで、幅広い候補者が立候補しやすくする提案もあります。
Q8. 供託金が没収される条件は何ですか?
A8. 一定の得票率に満たなかった場合、供託金は没収されます。衆議院選挙では有効投票数の10%未満、地方選挙では自治体ごとに定められた基準を下回ると没収対象になります。
Q9. 供託金が高額であることのメリットは何ですか?
A9. 候補者の乱立を防ぐことで、選挙運営の効率化や有権者の混乱防止につながります。また、一定の資金力や覚悟がある候補者が選挙に臨むことを促します。
Q10. 供託金が民主主義に与える影響は何ですか?
A10. 供託金制度は、経済的余裕がある候補者に有利に働き、経済的に困難な立候補者を排除する可能性があります。これにより、多様な意見の反映が難しくなり、民主主義の本質が損なわれるリスクがあります。
まとめ
選挙の供託制度について説明しました。
選挙の得票率が低いと供託金は没収されます。本来は売名目的の立候補を防ぐことが目的ですが、2024年の東京都知事選のように53名が供託金を没収されるという異例の事態が発生したケースもあります。
今後の供託制度の在り方について、議論がさらに進むことを期待しています。
【参考】
法務省 供託制度に関する外国法制等の調査研究業務報告書
参議院
時事ドットコム
なお、選挙制度について、以下の記事では選挙権が18歳に引き下げられた理由やその影響をまとめています。
選挙権18歳:18歳以上に引き下げられた理由とその影響、被選挙権の年齢引き下げに関する議論をまとめました
また選挙への立候補を考えている方向けに、有権者への電話アプローチの方法をマニュアルとともに解説しています。
投票を電話で依頼する方法を解説(有権者への電話アプローチのマニュアル例付き)
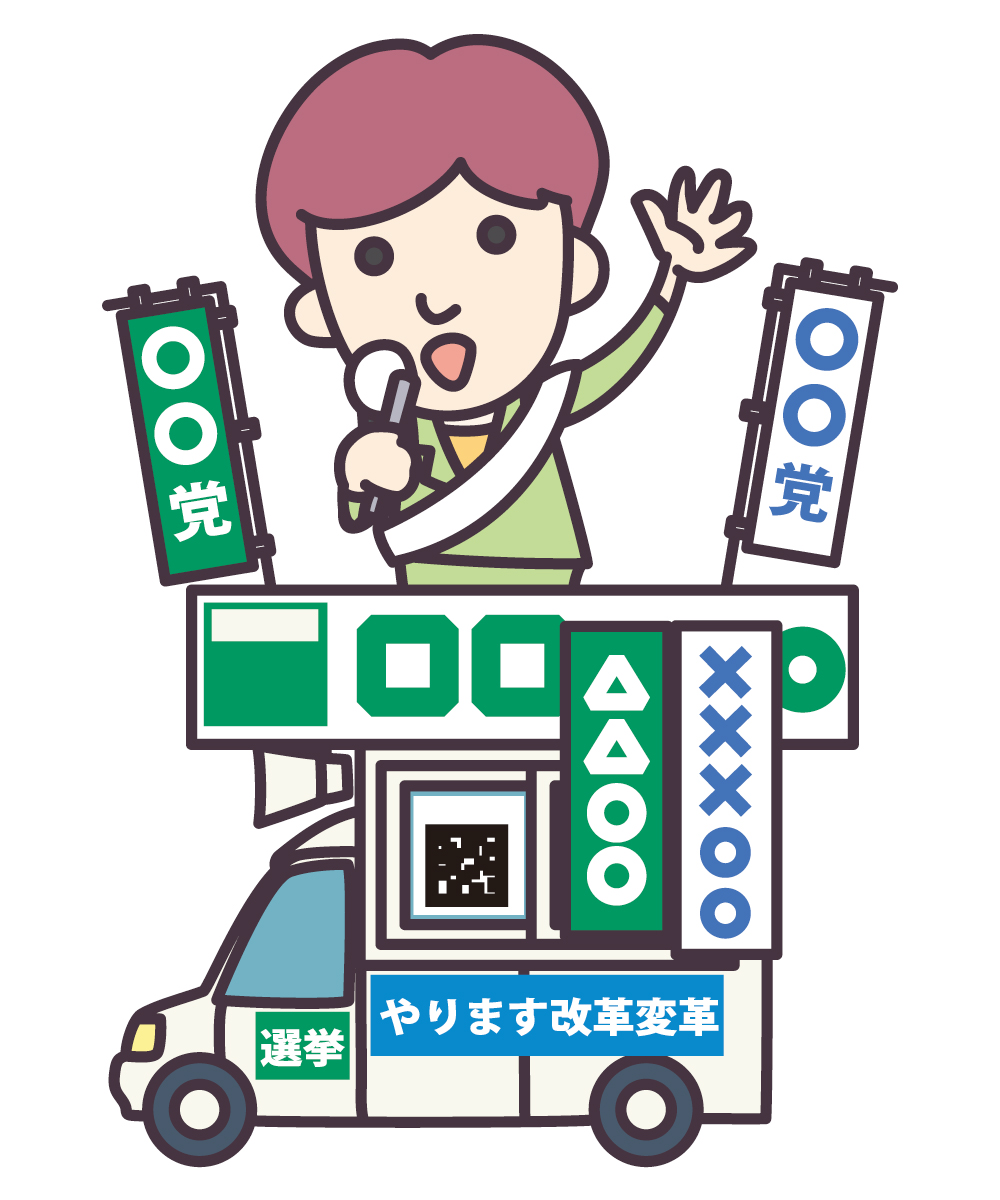


コメント