「政党交付金って何?何に使うお金?」
ニュースでときどき耳目に触れる政党交付金ですが、それが一体なのか、何に使っているお金なのか分かりにくいですよね。
ですが、私たちの生活にかかわる国政で使われているお金です。定期的に不正利用のニュースも流れますが、交付金がなくなることはありません。
政党交付金とは何か、なぜなくならないのかを知っておくほうが、今後の有権者としての意識や行動にも関係してきます。
そこで、政党交付金(政党助成制度)についてまとめて説明します。
※関連記事:政党内閣とは:日本で最初の政党内閣はどの総理大臣のときで、その後どうなったか
政党交付金とは
政党交付金とは、政党の活動を助けるために国庫から支出されるお金のことです。税金から各政党に支払われます。
国勢調査の結果をもとに、「250円×人口」の金額が毎年1月1日時点での各政党の議員数、選挙での得票率に応じて年4回(4月、7月、10月、12月)に分けて分配されます。
ちなみに2025年度の政党交付金は315億円あまりの予定とのことです(NHK政治ニュース「ことし交付予定の政党交付金 9つの政党に総額315億円余」より)。
※関連記事:議員立法とは:議員立法の手続きや特徴、成立する議員立法が少ない理由を解説
政党助成制度に基づいて支払われる
政党交付金とは、政党助成制度に基づいて支払われます。
政党助成制度は以下のように規定されています。
政党助成制度は、国が政党に対し政党交付金による助成を行うことにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とした制度です。
総務省HPより引用
つまり、政治活動を資金面で支援する制度です。これがないと、政治活動を行えるのがお金に余裕のある人ばかりになってしまい、政治への国民の声の反映が偏る恐れがあります。
大学の奨学金のようなものですね。
政党に対して交付される
政党交付金はその名のとおり、政党に対して支払われます。政治家個人には政党本部から分配されます。
2024年度の政党交付金はNHKの試算では以下のとおりです。
| 政党 | 交付金額 |
| 自民党 | 160億5300万円 |
| 立憲民主党 | 68億3500万円 |
| 日本維新の会 | 33億9400万円 |
| 公明党 | 29億800万円 |
| 国民民主党 | 11億1900万円 |
| れいわ新選組 | 6億2900万円 |
| 社民党 | 2億8800万円 |
| 参政党 | 1億8900万円 |
| 教育無償化を実現する会 | 1億1800万円 |
なお、共産党は制度の目的に反対しており、毎年政党交付金を申請していません。
政党交付金の交付条件
政党交付金が分配されるには一定の条件があります。国政政党であり、以下の2つの要件のいずれか1つを満たしている必要があります。
余った政党交付金は返還する
政党交付金は経費のように後払いではなく、事前の分配です。ですので、余るときもあります。
余った政党交付金は国庫に返還義務があります。返還された例は少ないですが、以下のような例があります。
政党交付金の財源はどこから?
政党交付金の財源は、国民の税金です。具体的には、一般会計予算から政党助成金として支出され、総額は年間約300億円程度です。
この金額は、すべての有権者に分配される形で計算され、一人当たり約250円程度の負担となります。
国民の税金を使う以上、政党交付金の使い道に対する透明性と説明責任が求められます。そのため、各政党は交付金の使途を報告し、公表する義務を負っています。
政党助成金との違い
ニュースなどでは、政党交付金、政党助成金という2種類の呼び方がされることがあります。前述の要因、政党助成制度に基づいて支払われるお金を政党交付金と呼ぶので、正確には「政党助成金」は存在しません。
とはいえ、習慣的に政党助成金と言われることもあります。「政党助成金=政党交付金」です。
政党交付金の使い道
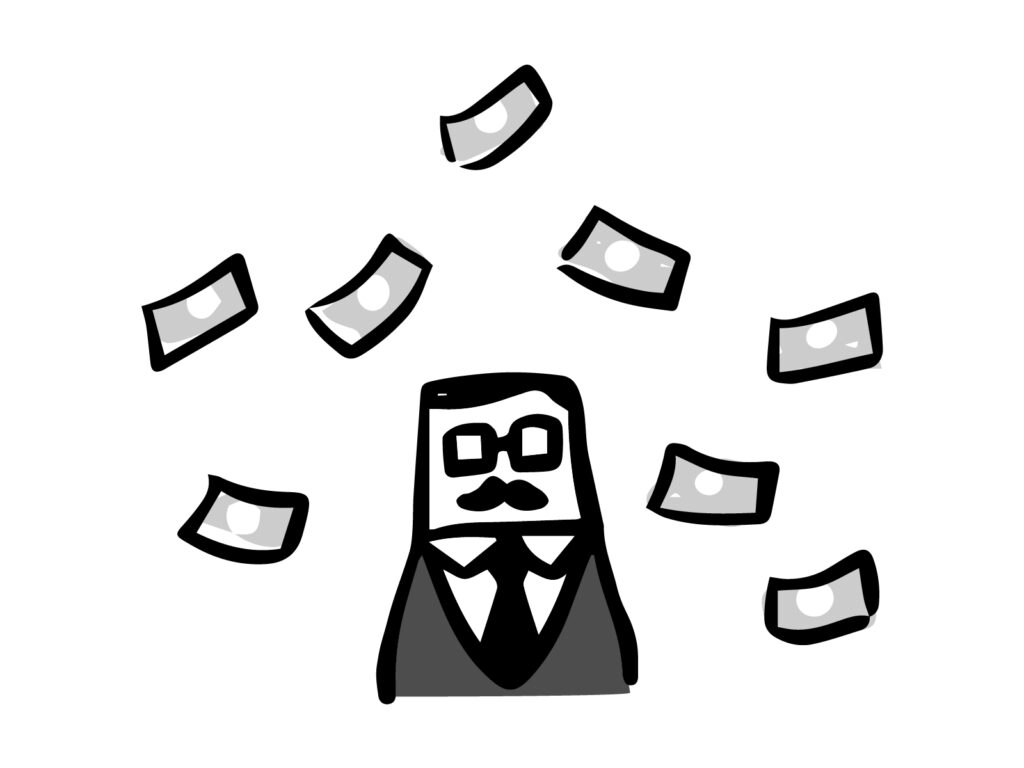
各政党の政党交付金の使い方の実例
政党交付金は、主に選挙活動や広報活動、政策立案費、事務所運営費などに使われます。例えば、大政党では交付金の一部をテレビ広告やポスター作成に投入し、選挙戦略を強化しています。
一方、小規模政党では、交付金が党本部や地方事務所の維持に優先的に使われることが多いです。
過去の例として、ある政党が広報活動費として全体の60%以上を費やしたことが明らかになり、選挙対策の中心的な資金源となっていることが伺えます。
政党交付金の透明性と課題
政党交付金の使用状況は、毎年の収支報告書として公表されますが、その内容は簡素で詳細に欠ける場合があります。これにより、一部では不正使用の疑惑が浮上することもありました。
過去には、交付金の一部を特定の政治家の個人的な活動に流用した事例が報じられ、制度の運用に対する批判が高まりました。
透明性を確保するためには、使途の詳細な公開や監査体制の強化が求められます。
なお、政治資金収支報告書について以下の記事で詳しく解説しています。
政治資金収支報告書とは:収支報告の報告義務はどこまで?違反するとどうなる?
政党交付金の問題点
政党交付金にはいくつか問題点も指摘されています。
政党交付金の不正利用

まず、政党交付金には使い道に制限がありません。
政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならないとされています。
総務省HPより引用
上記のように「適切に使用」とあるだけで、「適切」の範囲規定はありません。
ただし公開義務があります。過去には不適切な使用と指摘された例も多数ありました。
2007年玉澤徳一郎氏、領収改ざん
自民党で防衛庁長官や農林水産大臣を歴任した玉澤徳一郎氏にかんして、2004年分の領収書の領収書を偽造して重複計上していたことが2007年に発覚しました。
2007年に自民党を離れ、2008年に復党し、2009年に政界を引退しています。
2010年中島正純氏、架空支出計上
2009年に民主党から立候補して初当選した中島正純氏に関して、政治資金収支報告書に架空計上が指摘されました。
2009年に知人から車やPCをリースしたとして費用が計上されていましたがその事実はなく、2010年に民主党を離党しています。
2016年民進党富山県連、飲食や選挙費用に不正利用
2016年、民進党の富山県連本部で政党交付金の不正利用が発覚しました。
2010年から2015年までの6年間、坂野裕一氏と高田一郎氏が飲食費や架空の広報費・印刷費を計上していました。
2名とも除籍のうえ、政界を引退しています。
2022年日本維新の会トップの馬場氏に収支報告書虚偽記載の疑い
2022年、日本維新の会党首の馬場議員に、収支報告書虚偽記載の疑いが指摘されました。
2018年分、2019年分の収支報告書の金額が収支報告書と使途報告書それぞれに記載された金額にズレがありました。
※関連記事:政治資金収支報告書とは:収支報告の報告義務はどこまで?違反するとどうなる?
2024年杉田水脈氏、政治資金収支報告書記載もれ問題
自民党の杉田水脈氏が、2018年から2022年の間に政治資金パーティによるキックバックを1500万円以上得ていたにも収支報告書に記載していなかったとして刑事告訴されました。
ほかにも会合費の領収書がスナックや居酒屋、バーのものが多く、本当に政治活動による支出なのか疑問視されました。
問題発覚後、自民党から半年間の役職停止処分も受けています。
政党交付金目当てに駆け込み政党ができる
政党交付金発生には、「国会議員が5名以上」あるいは「前回の国政選挙で2%以上の得票率」という要件が必要です。これを狙って年末・年始に政党の離合集散をくりかえして「政党交付金をもらえる政党」を誕生させる可能性があります。
2014年生活の党
2014年12月、所属議員数が4名に減って政党交付金をもらえなくなる「生活の党」に山本太郎参議院議員が参加して議員数をギリギリ5名にするという事態が発生しました。
2015年日本を元気にする会、太陽の党
2015年1月、解党した「みんなの党」の元所属議員4名と「次世代の党」に所属していたアントニオ猪木参議院議員が強力して5名で「日本を元気にする会」が結成。政党交付金を獲得しました。
さらに同年・同月、「次世代の党」に所属していた園田衆議院議員が「太陽の党」に政党変えし、このおかげで太陽の党は政党助成金を獲得できました。
なぜ政党交付金が生まれたのか
前述のように、政党交付金の利用や収支報告に関して、不正利用が疑われるケースがたびたび発生しています。それにも関わらず、政党交付金が生まれて現在もなくならないのには理由があります。
なお、政治家の汚職を防ぐための法律である政治資金規正法について、以下の記事で詳しく解説しています。
政治資金規正法とは:政治資金スキャンダルと歴代内閣への影響、政治資金規正法改正の内容をまとめました
政治家の汚職を減らすため
政党交付金が生まれた最大の理由は、政治家の汚職を減らす(なくす)ためです。
1970年代から1990年代にかけて大物政治家による巨額の汚職が頻発しました。
1994年政党交付金の法令が成立
前述のような汚職事件頻発により、1994年についに政権が自民党から社会党へと移りました(55年体制の終焉)。
こうした世論の動きを受けて、1994年に政党助成法を含む政治改革四法が成立し、政党交付金の制度が誕生しました。
政治活動に多額のお金がかかる
そもそも、政治家が汚職や不正利用をしてでもお金をかき集めるのには理由があります。それは「政治活動に多額のお金が必要だから」です。
元衆議院議員の深谷隆司氏は月間Hanada2024年4月号で以下のように記しています。
「現役国会議員には公設秘書が三人付く。しかし、広い選挙区で政治活動をするには三人ではとても足りず、最低でも四~五人の私設秘書が必要で、その手当、人件費がかかる。/選挙区には当然事務所を開き、場所によっては数カ所必要なところもある。これらの維持経費は馬鹿になりません。/後援会活動に要する費用も大きく、仮に政治用パンフレットを作りこれを発送するとなると印刷費、郵送代と大変な費用がかかります。数万枚のパンフレットを年数回出さなければ主張を徹底して伝えることができないのだから、大変なのです。」
月間Hanada2024年4月号より引用

月刊Hanada2024年4月号 [雑誌]
政党交付金をなくしても別の分配金制度ができる
政治活動はお金をかけないといけないため(次の選挙で落選するため)、結局のところ、政党交付金をなくしたところで別の分配金制度ができるだけかもしれません。
使途の開示義務がある政党交付金は、まだチェックできる余地がある「マシ」な制度といえるかもしれません。
もちろん、おかしな使い方をして構わないお金ではありません。使う側のモラルやおかしな使い方のできないシステムの構築が必要でしょう。
他国との比較で見る政党交付金
他国の政党交付金制度の事例
他国では、日本と異なる政党交付金制度を採用している場合があります。例えば、ドイツでは政党の得票率に応じた資金が支給され、アメリカでは公的資金ではなく、主に寄付で運営されています。
他国と比較すると、日本の政党交付金制度の特徴がより明確になります。
政党交付金をめぐる国際的な課題
国際的には、政党交付金の透明性が共通の課題です。一部の国では、資金の流れを監視する独立機関を設けており、日本もこれを参考にできるでしょう。
また、各国の制度を比較することで、より効果的な資金配分方法が見えてきます。
政党交付金に関するQ&A
Q1: 政党交付金とは何ですか?
A: 政党交付金は、国が政党の活動を支援するために交付する公的資金です。1994年に政治資金の透明性を高める目的で導入されました。企業献金に依存せず、政治活動を安定的に行うための重要な制度です。
Q2: 政党交付金はどのように配分されますか?
A: 政党交付金は、各政党の議席数と得票率を基準に配分されます。具体的な計算式に基づいて交付額が決まり、大政党はより多く、小規模政党は比較的少額の交付金を受け取ります。
Q3: 政党交付金の財源はどこから来ていますか?
A: 政党交付金の財源は国民の税金です。一般会計予算から年間約300億円が支出され、有権者一人当たりの負担額は約250円と見積もられています。
Q4: 政党交付金はどのように使われていますか?
A: 政党交付金は、選挙活動、広報活動、事務費、政策立案費などに使われています。各政党が収支報告書を公開し、交付金の使途を説明する義務がありますが、透明性に欠けると指摘されることもあります。
Q5: 政党交付金のメリットは何ですか?
A: 政党交付金の主なメリットは、公平性を保ちながら政治活動を支えることです。企業献金に依存せず、利益誘導のリスクを低減します。また、安定した資金源を確保することで政党の活動基盤を強化します。
Q6: 政党交付金にはどのような批判がありますか?
A: 主な批判として、国民負担の増加や税金の使い道に対する不満が挙げられます。また、小規模政党や新興政党が不利になる配分基準や、不透明な使途管理が問題視されています。
Q7: 他国の政党交付金制度と日本の違いは何ですか?
A: 他国では、ドイツのように得票率に基づく配分や、アメリカのように公的資金を用いない寄付中心の制度があります。日本は議席数と得票率を組み合わせた独自の配分基準を採用しており、透明性と公平性の強化が課題です。
Q8: 政党交付金制度は今後どう改善されるべきですか?
A: 配分基準の見直しや、交付金の詳細な使途公開が求められています。また、国際比較を参考に、監査体制の強化や透明性向上を図ることで、国民の理解と納得を得ることが必要です。
まとめ
政党交付金(政党助成金)とは何かを、その仕組みや誕生経緯から説明しました。
一定の要件を満たした国政政党に対して、政治活動の資金的な助けにするために、日本の人口×250円が分配されます。使い道には公開義務があり、余ったお金は返還されます。
不正利用が後を絶ちませんが、政党助成金制度誕生以前のロッキード事件など巨額な汚職を減らすという目的には貢献していると言えそうです。
今後も、より良い政治が実践されるように、政党交付金も含めて制度が改善されていくと良いですね。



コメント